宝塚歌劇は1914年少女歌劇から始まり、110年以上にわたり日本のエンターテインメント史を彩ってきました。この記事ではプール改造劇場での初公演から国民的舞台へと発展した軌跡を、貴重な体験談を交えながら紐解きます。
誕生:温泉のプール劇場から始まった奇跡
1914年・温泉余興の実験
阪急電鉄創業者・小林一三が「家庭娯楽」を理念に「清く 正しく 美しく」は、小林一三翁の教えと共に“家族ぐるみで安心して楽しめる国民劇を目指した。
1911年に誕生した宝塚新温泉のプールを改造したパラダイス劇場で12歳~17歳までの少女17名による初めての宝塚少女歌劇第一回公演公演が行われました。観覧料は無料でした。演目は、桃太郎を題材としたお伽(おとぎ)歌劇『ドンブラコ』と『浮れ達磨』、ダンス『胡蝶』の全3本作品でした。
音楽学校の設立
1919年(大正8年)に宝塚音楽歌劇学校が創設され、本格的な教育のシステムが確立されました。卒業生による「宝塚少女歌劇団」が組織されて、現在まで続く「清く正しく美しく」の校訓が定められました。
華やかな夢の舞台を支える歌やダンスそして日舞、演劇といった芸能の基本はもちろんですが、礼儀作法やマナーをきちんとわきまえ、一人の女性として、社会人としての品格を忘れないように、と贈った言葉です。

「清く正しく美しく」その精神は、時代がどれほど移り変わろうとも、すべてのタカラジェンヌ、そしてスタッフの中に深く息づいています。
大正ロマンとレビューの革新
日本初のレビュー公演
1927年(昭和2年)『モン・パリ』で西洋風レビューを導入。時代の先取りとして日本初のレビューを上演。その主題歌「~うるわしの思い出 モン・パリ~♪」が流行歌として話題となり、日本の舞台芸術に新しい風を吹き込みました。昭和初期日本の文化にヨーロッパの要素を取り入れる新しい試みが行われました。
元銀行員の男性(95歳)の証言:
「昭和初期、給料の3分の1を貯めて月組公演を見に通った。トップスターが銀橋でウィンクした時、隣の紳士が感激のあまりシルクハットを投げたのが忘れられない」
組制度の確立
1921年(大正10年)花組・月組が誕生、1924年(大正13年)日本初の4,000人収容の宝塚大劇場が完成します。1925年(大正14年) 花・月・雪組の3組交代による年12公演体制が確立しました。
戦時下の灯火としての役割
暗黒時代の光
1944年(昭和19年)レビューの上演は中止されますが、歌劇団は奉仕隊を組織し、各地で慰問公演を行いました。終戦間近の1944年3月には、宝塚大劇場と東京宝塚劇場が閉鎖。元軍需工場勤務の女性(102歳)は「工員たちが劇場で涙しながら『同期の桜』を合唱した」と回想します。
戦後復活の奇跡
1951年(昭和26年)『虞美人』白井鐵造作のグランド・レビュー初の1本立て大作。焼け野原に咲いた華やかな舞台は、GHQ(連合国最高司令官総司令部)関係者も魅了し、宝塚歌劇の人気が再燃。暗く苦しい世相を吹き飛ばすかのような明るい華やかな舞台に注目が集まり、「日本の文化復興の象徴」と評されました。
戦後復興とブロードウェイの風
海外作品の本土化
驚異的な経済復興により、世間が国内から世界へと目を向けた時代、宝塚歌劇は海外の力を取り入れるようになっていった。1967年(昭和42年)宝塚歌劇初の外国ミュージカル『オクラホマ!』を上演、1968年(昭和43年)『ウエストサイドストーリー』といった、初のブロードウェイ作品上演となりました。芸術祭賞大賞を受賞する。
1987年(昭和62年) 月組公演『ME AND MY GIRL』上演、1996年にはウィーンのミュージカル雪組『エリザベート』では死神トート役の一路真輝が「黒い翼」の衣装でセンセーションを巻き起こしました。その後何度も再演され、宝塚の新たな代表作となっています。
2008年(平成20年) ブロードウェイミュージカル『THE SCARLET PIMPERNEL』を星組で上演、2010年(平成22年) 星組梅田芸術劇場公演『ロミオとジュリエット』上演された。2015年(平成27年)『1789 -バスティーユの恋人たち-』月組にて初の上演です。
空前のタカラヅカブーム
1974年(昭和49年)『ベルサイユのばら』大ヒット。この作品は池田理代子原作のアニメを宝塚歌劇で初の舞台化。1976年までに各組で上演、観客合計140万人という空前の大ブームとなりました。当時大学生だった男性(70歳)は「徹夜で並んだチケット入手作戦」をブログに綴っています。
ベルばらブームと現代への飛躍
文化現象の誕生
『ベルサイユのばら』は単なる舞台を超え、ファッションやライフスタイルに影響。『ベルサイユのばら』コラボのファッション新コレクションが発表されたり、コラボグッズもたくさん発売されています。2025年に完全新作劇場アニメの上映が決定『ベルサイユのばら』が、サンリオキャラクターズとコラボすることが発表されています。
テクノロジーとの融合
2022年宙組公演『FLY WITH ME(フライ ウィズ ミー)』メインテーマ曲「FLY WITH ME」(のミュージックビデオを、全編フルCGで制作されました。ボリュメトリックビデオ技術を駆使して撮影した3D映像に、360度視点のダイナミックなカメラワークとフルCGによる背景を組み合わせた、新感覚の映像作品です。

デジタル技術と宝塚歌劇のパフォーマンスが融合した新たなフルバージョン映像を期間限定で、宝塚歌劇の動画配信サービス「TAKARAZUKA ON DEMAND」で配信(有料)されました。
ファンが語る「私と宝塚の歴史」
3世代にわたる愛

祖母、母、娘という親子3世代にわたる宝塚ファンはとても多く色々なエピソードがあります。「祖母(大正生まれ)は戦前の月組スター・小夜福子のブロマイドを大切にし、母(昭和20年代生)は雪組の『風と共に去りぬ』で涙し、私は宙組の『ファントム』にハマりました。家族旅行は常に宝塚観劇計画から始まります」(30代女性・ファン歴20年)
男性ファンの変遷
「1980年代は劇場で男性1人だと奇異な目で見られましたが、今では専用SNSコミュニティが存在。2019年の星組『ロミオとジュリエット』では隣席のサラリーマンと自然に感想を交わすまでに」(50代男性・ファン歴30年)
国際化するファン層
宝塚歌劇が映像が世界で配信されるようになり、海外から歌劇を観に来る人がたくさんいます。大好き過ぎて宝塚に住んでいるアメリカ人や韓国人もいます。ヨーロッパやアジアからも公演毎に日本に観に来る人もたくさんいます。
結び:未来へ続く虹の架け橋
宝塚歌劇は、プール劇場の乙女たちから始まり、戦争・高度成長・バブル崩壊を乗り越え、常に時代の鏡として進化を続けてきました。創設者・小林一三が夢見た「国民劇」は、今や全世界配信されるグローバルエンターテインメントへと羽ばたいています。劇場の香り、生演奏の振動、スターの眼差し、この100年の歴史が紡いだ夢は、これからも新たな物語を生み続けます。


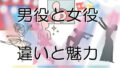
コメント